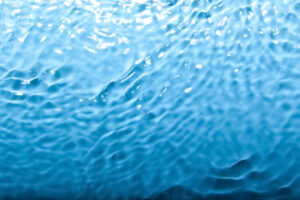オースティン・アイヴリー著
訳 DeepL 12月6日
レオ14世教皇の選出から半年が経ち、カトリック教会がヨーロッパ文化に根ざしていた長い時代が、ヨハネ・パウロ2世とベネディクト16世の教皇職をもって終焉を迎えたことは明らかである。フランシスコ教皇、そして現在のレオ教皇は、新たなグローバルでポストモダンな時代を切り開いた。
教会はいま、何を失い、何を求めているのか
教区で「共同体性に関するシノドス」を説明する講演をするたび、「司祭や司教からこの件について何も聞かされない」と言われる。当初は伝達不足への不満かと思ったが、その痛みはより深い。 方向性やビジョンが欠如しているのだ。人々は信徒数の減少と高齢化、教区の統合や閉鎖、若者のいない空席の礼拝席を目の当たりにしている。彼らは死を目の当たりにしながら、なぜそれが起きているのか、その後に何が来るのかを理解しようと苦闘している。神がどこにおられるのか、未来のビジョンは何かを知りたいと願っている。なぜなら、このまま従来通り続けていくわけにはいかないはずだからだ。
信仰の感覚と聖霊の導き
これは信仰の感覚―信じる人々の信仰の本能―が働いているのです。彼らが問うのは当然です。なぜなら聖霊は教会に語りかけてきたからです。 時代の徴の識別が行われ、それと共に一つのビジョンが示された。この新たな時代に福音を伝えるために、教会が今どう変容すべきかというビジョンである。この識別は共同体性に関するシノドスよりずっと以前から存在していたが、シノドスによって確認された。それはフランシスコ教皇の在位期間を形作ったビジョンであり、今やレオによって推進されている。私はこれを「アパレシーダの道」と呼ぶ。
アパレシーダの道とは何か
アパレシーダという出来事
アパレシーダとはポルトガル語で「現れた」を意味する。ブラジルの国宝聖地ノッサ・セニョーラ・ダ・アパレシーダ(サンパウロの北東約160キロ)の中心には、1717年にパライバ川の貧しい漁師たちの網に現れた聖母の小さな像が安置されている。次の漁では魚が大量に獲れ、漁師たちは港に戻らざるを得なかった。 この (奇跡)は数多の奇跡の始まりであり、聖ペテロ大聖堂に次ぐ世界最大の大聖堂建設へとつながる信仰の礎となった。
2007年アパレシーダ会議
2007年5月、ラテンアメリカ司教団がアパレシーダで画期的な3週間の会合を開き、その結論文の起草をブエノスアイレスのホルヘ・マリオ・ベルゴリオ枢機卿が担当した。 アパレシーダはフランシスコ教皇の教皇職の方向性を定めた――そしてレオ教皇の方向性も定めたのである。その成果は単に現代という時代(「時代の転換」とアパレシーダは呼んだ)を捉えただけでなく、より重要なことに、この新たな状況下で福音宣教を行うために、聖霊が教会に改革を求めていることを理解した点にある。
これは現時点の教会において他に類を見ない未来像である。ロードマップにそう言えるなら、それはペンテコステの雰囲気を帯びている――そして出席者も神学者たちもそう認識した。 例えばクロドヴィス・ボフは、これは地域司教団がこれまでに作成した中で最高の文書であるだけでなく、「聖霊の驚き」だと述べた。なぜなら、誰もそのような質の高い文書を予想させるものは何もなかったからだ。
さらに重要なのは、アパレシーダへの道筋が示されたことだ。これはラテンアメリカ・カリブ海諸国司教協議会連合(CELAM)の第5回総会であり、世界カトリック信徒のほぼ半数が暮らす大陸をカバーする地域組織の集まりであった。15年ぶりの総会でもあった。 しかし過去の総会とは異なり、前例のない3年間の協議と識別プロセス——現在「シノダリティー」と呼ばれるプロセス——によって準備された。大陸全域で、地方・国家・地域レベルを問わず、率直で厳しい問いが投げかけられ、一般信徒が回答を求められた。調査研究が委託され、専門家が教会を社会・メディア・若者がどう見ているかを分析した。 私は2006年、コロンビアのボゴタで開催されたこうした会議の一つに招かれ、その様子を『ザ・タブレット』誌に寄稿した。このプロセスの謙虚さに驚き、欧州では考えられないことだと記した。当時、地域教会が実施した同種のプロセスとしては、断トツで最大規模のものだった。
時代の転換という診断
大陸の司教たちが聖堂に集う以前から、文書には「時代の転換(cambio de época)」という表現が現れ始めていた。 これはフランシスコ教皇が『福音の喜び』で「時代の転換」と訳した表現であり、レオ教皇も選出以来頻繁に使用している。この概念は社会学者が区別する「変革の時代」——既存の安定した文化的枠組み内で社会変化が起こる段階——と「時代の転換」——急速な社会・技術的進歩が人間の文化理解能力を超え、その枠組みを破壊する段階——に由来する。 通常数十年続く時代の転換は、ある時代から次の時代への激動の移行期である。制度は機能不全に陥り、エリート層は無力かつ自己保身に走る。無力感を抱いた人々は緊張と不安に苛まれる。
アパレシーダは、教会が福音宣教に失敗し始めていることを見抜いた。信仰の伝達手段はほつれ、断絶しつつあった。制度と民衆の間に隔たりが生じていたのである。 文書は「時代の変化が『伝統的な生活様式、関係性、コミュニケーション、信仰の伝承』に影響を与えている」と指摘し、グローバル化、個人主義、制度の弱体化、大叙事の崩壊、人々の移動、生態学的危機、そして法と文化からキリスト教的価値観が排除される現象を強調した。これに対しアパレシーダは「霊的・牧的・制度的改革を伴う教会の刷新」を求めた。
フランシスコからレオへ ― 継承されるビジョン
聖堂での毎日のミサの一つで、ベルゴリオ枢機卿は有名な説教を行い、教会をルカ福音書に登場する腰の曲がった女に例え、自己に閉じこもり「神の民はあちらに」いると語った。 人々が教会を離れるというより、教会が人々から離れているのだ。ベルゴリオは教会が「自らから出て行く」必要性を説き、既存の枠組みや思考を超越し、聖霊に導かれて辺境へと向かうべきだと語った。 集まった200人の司教たちは、彼の言葉を聞いて「聖霊に油注がれた者」だと確信し(複数の司教が私にそう語った)、立ち上がって拍手を送った。6年後、2013年3月にローマで枢機卿たちに向けた演説で、ベルゴリオは同じイメージと言葉を用いて同じ診断を下した。彼らも拍手した。そして彼を教皇に選んだ。
フランシスコは就任後数か月間、訪問者にアパレシーダの文書を渡し、「私の意図を理解したいならこれを読め」と語った。しかし2013年11月、『福音の喜び』が発表された。ベルゴリオが200ページに及ぶアパレシーダ文書をまとめるのを助けた同じチームが、フランシスコのこの感動的な勧告書の執筆を支援した。この文書はアパレシーダの精神を普遍教会に定着させたのである。 こうしてフランシスコの選出――特に『福音の喜び』――は、ラテンアメリカ教会が今日の普遍教会の「源」となった瞬間を刻んだ。歴史を通じて地域教会は源となり、他の教会がそれを反映してきた(反宗教改革期のスペインやイタリア、第二バチカン公会議時のフランスやドイツを想起せよ)。
2025年5月8日の見出しは、当然ながら初の北米出身教皇の選出に関するものだった。しかしレオの教会論的ビジョンという観点では、より重要なニュースは枢機卿たちが第二のラテンアメリカ出身教皇を選出したことである。ロベール・プレヴォストは、ペルー教会における数十年にわたる司祭・宣教師・司教としての経験、そしてアパレシーダで成熟したビジョンによって深く形作られているからだ。 5月10日、枢機卿たちに向けてレオが「フランシスコが始めた旅路を継続する」と語った際、彼は「フランシスコが『福音の喜び』で示した第二バチカン公会議の道筋の刷新」を誓約した。
これを解読しよう。「第二バチカン公会議の刷新」とは、ラテンアメリカ教会が長年、大陸的使命として語ってきたものであり、「フランシスコが『福音の喜び』で示した第二バチカン公会議の道」とは、言うまでもなく、アパレシーダで成熟したラテンアメリカ教会による第二バチカン公会議の受容を指す。
宣教・回心・共同体性という三つの柱
レオは同勧告から「基本点」と呼ぶ項目を列挙し、その中からアパレシーダの「時代の転換」を見極める上で核心となる三点を挙げた:宣教におけるキリストの首位性への回帰、教会の宣教的回心、そして神の民の主体性と信仰の感覚を指す「共同体性」である。
したがって、2025年のコンクラーヴェの物語とは、アパレシーダからの道のりの延長と深化である。レオの選出は、フランシスコ時代が一部が望んだように今や棚上げできる章ではなく、次世代にわたって展開される新たな物語の始まりであることを示した。 チェコの司祭であり預言者でもあるトマーシュ・ハリークが私に語ったように:ヨハネ・パウロ二世とベネディクト十六世がヨーロッパ教会の近代との対話の長い時代を締めくくったならば、フランシスコは新たなグローバルなポストモダン時代の最初の教皇である。これに付け加えれば:レオは第二の教皇である。
アパレシーダで最も重要なことは、回心への道における最初で本質的な一歩、すなわち幻想的な自足性の放棄と謙虚さの受容であった。アパレシーダ文書は、世俗化を「混乱や危険、脅威しか見ない者たち」が「陳腐なイデオロギーや無責任な攻撃」で応じている現状を否定することから始まった。 ラテンアメリカ司教団は本質的に問うた。「我々は何をなすべきか?この新たな状況下で使命を果たすため、聖霊は我々にどのような変革を求めているのか?」教会はしばしば、第二バチカン公会議が求めた歴史的意識―時代の徴候を見極めること―を受け入れることに失敗してきた。歴史的変遷に応じた識別と改革の代わりに、嘆きと非難がデフォルトとなっていた。 だからこそベルゴリオは、ルカによる福音書の「腰の曲がった女」のイメージを用いて、自らを閉じこもり、純粋さの棘だらけの孤島と化した教会を描いたのである。
教皇フランシスコは2022年、ケベック州の司教・聖職者・牧会者への演説で、世俗化への否定的な反応と識別に基づく反応を対比させ、この点を明快に説明した。否定的な反応は権力と影響力の喪失、そしてその回復方法に焦点を当てる。キリスト教ナショナリズムや文化戦争戦略の姿勢である。 これはキリスト教的対応ではないとフランシスコは述べた。なぜならそれは受肉を否定し、権力や社会的存在感への世俗的執着を露呈するからだ。一方、識別的な対応は、そうした執着が不健全であることを謙虚に認めつつ、回心の賜物へと私たちを開く。世俗化における権力 と地位の喪失を受け入れることで、教会は謙遜のうちに神の慈悲をより良く証しできるのだ。
アパレシーダの司教団にとって、キリスト教がもはや「宗教」(religio)―文化や制度を通じて継承されるアイデンティティ―ではないことは明らかであった。大衆向けで文化的に媒介されたキリスト教の時代は終わり、我々は新たな使徒的時代にある。教区・学校・家族はいずれも依然として重要である―アパレシーダ文書はこれらに多くのページを割いている―しかし、単に従来通り継続しようとするならば、グローバル化した個人主義と消費主義という新たな文化に抵抗することはできないだろう。 信仰は今や、初期教会のように伝染のように人から人へと広がり、神の慈悲との出会いの体験を含まねばならない。アパレシーダが「第一の出会い」と呼んだこの体験がなければ、典礼、秘跡の準備、教義はますます意味を失っていく。
ブエノスアイレスでベルゴリオ枢機卿が行った一連の講演では、変化が不可欠だと繰り返し強調された。教区が信仰の生きる共同体——単なる秘跡のサービスステーションではなく、帰属と交わりの場——とならず、教会が信仰に形成された宣教的弟子を育て、神の国のために働き、キリストとの出会いを可能にしない限り、福音宣教は次第に意味を失っていく。アパレシーダはこの変革を「牧会的・宣教的回心」と呼んだ。 司祭は奉仕活動とカリスマを育み、参加と交わりを築き、神の民の責任と主体性を形成する手助けをしなければならない。「広義における市民性の構築と、信徒における教会への帰属意識の構築は、単一かつ唯一無二の運動である」とアパレシーダは述べた。
この最大の障害は、フランシスコが「聖職主義」と呼んだもの、すなわち聖職者が全ての権威と主体性を独占し、教会が聖職者と同一視される聖職者制度の腐敗であった。 信徒たちは洗礼による責任を回避するため、この二層構造の教会に共謀する。『福音の喜び』はアパレシーダ宣言実施6年間の傷跡を刻んでいる。そこには抵抗の規模と広がりが露呈していた:現状維持の「 」的思考の灰色の凡庸さ、過去の典礼への郷愁、遠ざかり抽象化された自己言及的な「博物館」的教会、 教会、司祭たちが説く「慈愛なき道徳主義」(eticismo sin bondad)、陳腐で味気ない説教の中で王国を一連の倫理的戒律に還元する姿勢。フランシスコは霊的世俗主義、怠惰、ペラギウス的自己依存、そして「不安に満ちた自己中心的な不信」に屈する者たちの「不毛な悲観主義」に立ち向かった。それは強力な強壮剤であった。
しかし『福音の喜び』は、アパレシーダが求めた回心を受け入れる喜びをも証ししている。最も胸躍る箇所は、神の民の中に聖霊の命が燃え上がり、その福音宣教のエネルギーが解き放たれることについてである。 フランシスコは繰り返し、恵みの優先性、道徳的・宗教的義務に先立つ神の救いの愛、最も貧しい者たちにおけるキリストの臨在、民衆の信仰の伝道力、そして神の国宣教の優先性へと立ち返る。これは教会が「自らから出て」聖霊の力を受け入れ、キリストを中心におくときに起こる事象についてである。 それは時代の変革の中で、自己のためではなく使命のために生きることを学ぶ教会である。ペルーにおけるレオの生涯を読むと、プレヴォストがこのビジョンの中でいかに確固として活動していたかに驚かされる。彼が5月10日に『福音の喜び』を現代における第二バチカン公会議の再活性化として語ったとき、彼自身も2014年以降のチクラヨ司教としての実践経験から語っていたのである。
教皇交代期、私はインタビューでしばしば問われた――フランシスコ教皇の遺産とは、様式の改革か、それとも本質的な改革か? しかし福音宣教において、様式こそが本質である。第二バチカン公会議の偉大な歴史家、ジョン・オマリー神父は、様式こそが公会議における「問題の背後にある問題」の第一であり、他の二つは共同体性と歴史的自覚であると述べた。 様式の課題とは、教会が人類とどう関わるかという問いであった。近代の新キリスト教世界観から生まれた法的な命令統制様式か、それとも世俗時代にふさわしい牧会的様式——すなわち同行し、促し、励ますなど——か。 公会議における画期的な進展は、ポスト・キリスト教社会において、教会が権力の論理と言語を放棄することで、神が私たちと関わる方法——すなわち「足を洗う」行為——をより良く反映できると認識したことである。
神のスタイルと優しさの文化
フランシスコはこれを「神のスタイル」と呼んだ。戦場病院、教会は関所ではなく母であるといった、耳に残る比喩でこれを表現した。そしてもちろん、彼は言葉、行動、選択、計画のすべてにおいてこれを体現し実践し、近くにおられ具体的であり、優しく慈悲深く、注意深く見分け、謙虚で寛容な神を示した。 人々はフランシスコによって見られ、認められ、価値ある存在として扱われていると感じた。彼の存在の中で生き返り、自らの尊厳に目覚めたのだ――イエスに出会った人々と同じように。彼はこれを「優しさの文化」と呼んだ。彼にとっては自然なことであったが、それは意識的な選択でもあった。教会が神のスタイルを受け入れる必要性は、アパレシーダの識別でもあり、信徒たちにイエスが人々に与えた影響を黙想するよう招いている。 フランシスコにとって教会はこの様式を体現すべきであり、ローマ教皇庁から始めるべきであった。取引的で非人格的な権力のこの時代に人々が神を求めて訪れる時、彼らの心が切望するのはまさにこの神性の質である:権力(potestas)ではなく奉仕(ministerium)。この時代の「使い捨て文化」に対比される「優しさの文化」である。
そしてこの「スタイル」の問題において、私は特にフランシスコの川がレオの川へと溢れ出ているのを見る。枢機卿団の最高位者であるジョヴァンニ・バッティスタ・レ枢機卿は、フランシスコの葬儀での説教で、彼の「現代の感性に共鳴する『受け入れと傾聴のカリスマ』が、道徳的・霊的エネルギーを目覚めさせようと、人々の心に触れた」と語った。 枢機卿たちはその後ロベール・プレヴォストを選出し、彼が彼らと共にいる姿勢――その優雅さ、傾聴する姿勢、合意形成能力――に深く感銘を受けたことを説明した。明言するかどうかは別として、枢機卿たちは時代の転換期における福音宣教の鍵が、神のスタイルを備えた教皇にあることを理解していた。 信仰の内容、すなわち「信仰としての信仰(fides quae)」(教義)は依然として重要である。しかし、今やその入り口は「信仰としての信仰(fides qua)」―信仰の在り方、すなわち心構えや生き方にある。
これは理にかなっている。教会が国家と結びつく以前の使徒時代、キリスト教共同体は富や地位によって (人々を魅了)したのではなく、忍耐(patientia)という習慣性——神の御業を確信して待ち望む中で生き、耐え忍ぶ意志——によって人々を惹きつけた。彼らの心構えは八福の喜びと希望に満ち、その行動は神の無差別な慈愛(caritas)を映し出していた。
教会はどのように神の様式を体現するのか。それは「共議制」の賜物であり、フランシスコの下で牧会的・宣教的回心の本質的手段と見なされるようになった。これもアパレシーダに遡る:「恒常的な牧会的回心」とは、神の民全体――信徒、修道者、司祭、司教――が時代の徴を通じて教会に語りかける聖霊の声に耳を傾け、識別するとき起こる現象である。
シノダリティという実践の道
フランシスコはこのビジョンを、2017年10月17日に司教シノドス創設50周年を記念して行った有名な演説で展開し、シノダリティに関するシノドスにおいて具体化した。それは神の民全体がその主体性を発見するためであった。 「シノダリティに関するシノドス」の旅のテンプレート——霊的対話を通じた民衆への諮問、続いて国家・地域レベルでの識別段階、そして司教会議での集結——は、アパレシーダへの道程で創り出された。そしてシノドスの最終文書をアパレシーダ/『福音の喜び』と並べてみると、その類似性は驚くべきものであり、聖霊が現代の教会に語りかけていることのさらなる証拠である。 シノダリティがコンクラーヴェで注目された話題となったのも当然である。
「シノダリティの過程を通じて」と教皇レオは9月19日にローマの聖職者たちに語った。「聖霊は教会刷新への希望を鼓舞された。それは共同体を活性化し、福音の様式において、神との親密さにおいて、そして世界における奉仕と証しの存在において成長させるものである」 教皇はさらに、共同体性の実り——すべての奉仕と賜物を尊重し、すべての参加を可能にし、識別と共同責任の習慣を育むこと——を、アパレシーダの言葉そのものを使って説明した。そして、従来通りのやり方では不十分であり、養成が急務であることを明らかにした。 「私たちは形成の緊急事態を生きている」と彼は述べた。「キリスト教共同体の活力を維持するために、いくつかの伝統的な活動を続けるだけで十分だと錯覚してはならない。それは (十分ではない)のだ」
シノドスの最終文書は昨年10月に承認され、教皇の教えの一部となった。今年3月、フランシスコ教皇は、教会があらゆるレベルでその実施に関与する3年間の受容プロセスを承認した。 レオは6月にこのプロセスを確認し、7月にはローマのシノド事務局が実施指針を発表。多くの地方教会が「熱心にシノダリティを追求」している一方、躊躇したり初歩的な段階にある教会もあると指摘した。シノド実施段階の道筋(Pathways for the Implementation Phase of the Synod)は、抵抗する司教たちに対し「まず自らの抵抗に耳を傾けることで、聖霊の働きに自らを開く必要がある」と述べている。
結論|私たちの岸辺に届いた道
沈黙の一年を経て、イングランド・ウェールズ司教団は今週の総会でシノダリティを議題に掲げた。「何が起きているのか?なぜ何も聞こえないのか?」と問いかけてきた人々を思い返すとき、私は司教たちがこの時代の課題に立ち向かうよう祈らずにはいられない。それは福音の伝達を意味する――フランシスコ教皇、そして今やレオ教皇のもとで時代が識別され、聖霊が教会に語りかけたという事実を。 道は開かれている。ブラジルで始まり、ローマを経て、今や我々の岸辺に到達した。この道がもたらしたものを我々が受け入れるならば、それは必ずや我々を前進させるだろう。
オースティン・アイヴリーはオックスフォード大学キャンピオン・ホールにて現代教会史のフェローを務める。
本記事は、国際カトリック週刊誌『ザ・タブレット』2025年11月15日号に初掲載されたものです。オースティン・アイヴリー氏の許可を得て全文を転載・使用しています。